児童や生徒など、子どもの教育や支援に関わってみたいと考えている方にオススメしたい放課後等デイサービスでのお仕事。
- 放課後等デイサービス(放デイ)とは?
- 放課後等デイサービス(放デイ)での仕事内容とは?
- 放課後等デイサービス(放デイ)で働いている職種は?
- 放課後等デイサービス(放デイ)で働くために持っていると役立つ資格は?
- 放課後等デイサービス(放デイ)で働くやりがいとは?
今回は、放課後等デイサービスの仕事内容や必要な職種、持っていると役立つ資格、放課後等デイサービスで働くやりがいについて詳しく解説します。
放課後等デイサービスの利用を検討されている方はこちらの記事をご覧ください。
 放課後等デイサービスとは?対象者やサービス内容、利用までの流れを徹底解説!
放課後等デイサービスとは?対象者やサービス内容、利用までの流れを徹底解説!
記事でわかること
放課後等デイサービス(放デイ)とは?
放課後等デイサービス(放デイ)とは、就学している障害を持つ子どもに対し、学校の授業終了後もしくは休日において、生活能力の向上のために必要な支援や社会との交流の促進を図る便宜を提供する児童福祉法に基づくサービスです。
利用する子どもとその保護者のニーズが多様化する中でも、「障害を持つ学齢期の子どもの健全な育成を図る」という支援の根幹があります。
放課後等デイサービス(放デイ)の対象者
放課後等デイサービスの対象者は、小学生から高校生までの児童・生徒です。
基本的には身体障害、知的障害、発達障害を含む精神障害のある児童が対象ですが、児童相談所や市町村保健センター、医師により療育の必要性が認められた児童・生徒も対象となります。
つまり、障害者手帳や療育手帳は必須ではなく、療育が必要であるとして「受給者証」の発行がなされることで、放課後等デイサービスを利用することが可能です。
発達障害について詳しく知りたい方はこちらの記事をチェック!
 発達障害を知る~様々な特性から見る接し方や療育・支援までの流れ~
療育について詳しく知りたい方はこちらの記事をチェック!
発達障害を知る~様々な特性から見る接し方や療育・支援までの流れ~
療育について詳しく知りたい方はこちらの記事をチェック!
 療育とは?~児童発達支援や放課後等デイで働きたい方が気になることをまとめました~
療育とは?~児童発達支援や放課後等デイで働きたい方が気になることをまとめました~
放課後等デイサービス(放デイ)と児童発達支援の違い
放課後等デイサービスと児童発達支援はどちらも児童福祉法における通所サービスではありますが、放課後等デイサービスの利用対象者の年齢が小学生~高校生の児童・生徒であるのに対し、児童発達支援の利用対象者の年齢は0~小学校入学前の未就学児です。
放課後等デイサービスを利用する前に児童発達支援を利用している子どももおり、連続性を持った療育・支援を提供しているケースもあります。
児童発達支援では保護者が事業所やセンターまで送迎を行うことが一般的ですが、放課後等デイサービスでは自宅や学校から事業所までの送迎業務を行っていることが一般的という違いもあります。
児童発達支援について詳しく知りたい方はこちらの記事をチェック!
 児童発達支援とは?仕事内容や職種、持っていると役立つ資格、やりがいについて詳しく解説!
児童発達支援とは?仕事内容や職種、持っていると役立つ資格、やりがいについて詳しく解説!
放課後等デイサービス(放デイ)の仕事内容
放課後等デイサービスでは、利用する児童・生徒に対する「個別支援計画」に基づいた支援の提供を行っています。
個別支援計画とは、利用する児童・生徒一人ひとりの障害特性や発達段階に応じて、保護者からのヒアリングも踏まえた課題に対する目標を設定した支援計画のことで、児童発達支援管理責任者が作成します。
子どもに対して具体的にどのような支援を提供しているのか、詳しく見ていきましょう。
子どもの最善の利益の保障
障害の有無に関わらず、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を図るものとして、利用する児童・生徒に対して、家庭や学校とは異なる時間や空間、人、体験などを提供するのが放課後等デイサービスです。
放課後等デイサービスで子ども一人ひとりの障害特性や発達段階に応じた療育・支援を提供することが子どもの将来に繋がっていくのです。
自立支援と日常生活の充実のための活動
利用する子どもの発達段階に応じて、必要な基本的日常生活動作や自立生活支援を提供します。
具体的には、子どもが通っている学校と連携を図りながら、学校で行われている教育活動を踏まえて、子どもが意欲的に参加することができる遊びを行います。遊びを通して、成功体験を重ねさせることで、子どもの自己肯定感が育まれ、将来的な自立や地域での生活に繋げられるようにサポートを行います。
創作活動
創作活動は、表現することの喜びを体験することを目的としています。
工作や塗り絵などの手を動かして行う活動はもちろんですが、自然に触れる機会を設け、四季の移り変わりを肌で感じ、豊かな感性を養うことも含まれます。
地域交流の機会の提供
障害を持つ子どもは、障害があるということで社会生活において様々な経験をさせることが難しいケースがあります。
放課後等デイサービスでは、他の社会福祉事業者や自治体において実施されている体験活動や交流活動と連携し、利用する子どもの社会経験の幅を広げる活動も行っています。
積極的に地域交流を図ることで、将来的な自立に向けた周囲からの支援を得られる可能性が拡がります。
余暇の提供
放課後等デイサービスでは、事業所によって多彩な活動・支援プログラムを用意しています。
子どもがやりたい遊びができる環境や、リラックスした状態で過ごすことができる環境を用意して、「自分で何をするのか選択する」という行動を促します。
共生社会の実現に向けた後方支援
放課後等デイサービスでは、専門的な知識や経験をもとに必要に応じて放課後児童クラブや児童館などのバックアップを行う後方支援を実施しています。
また、保育所などを利用する障害を持つ子どもに対しても保育所等訪問支援を積極的に行い、地域における障害児支援の専門機関として相応の事業展開を行うことが期待されています。
保護者支援
放課後等デイサービスの支援対象者は基本的に児童・生徒ですが、その保護者に対する支援も行うことがあります。
- 子育ての関する相談支援
- ペアレント・トレーニングを通した子どもの育ちを支える力を身につけるための支援
- 保護者が子どもから離れた時間を確保するために、ケアの一次代行支援
学校や医療機関、専門機関との連携
放課後等デイサービスの役割の1つとして、学校や医療機関、相談支援事業者などの専門機関との連携を図ることも挙げられます。
| 関係機関 | 連携内容の例 |
| 学校 |
|
| 医療機関 |
|
| 相談支援事業所 |
|
| 保育所・児童発達支援 |
|
上記はあくまでも一例です。この他に放課後児童クラブや自治会、子どもが他に利用している放課後等デイサービス、地域自立支援協議会、など、様々な関係機関と連携を取って、様々な角度から一貫した支援を提供できるようにすることが大切です。
送迎業務
子どもが放課後等デイサービスに通うために、自宅や学校まで車両で迎えにいき、サービス提供時間が終了したら自宅まで送り届ける業務を行います。
送迎ドライバーとして専従している方がいる事業所もあれば、児童発達支援管理責任者や児童指導員などが送迎を行っているケースもあります。
放課後等デイサービス(放デイ)の1日のスケジュール
放課後等デイサービスにおける1日の業務スケジュール例(学校のある日)を見ていきましょう。
放課後等デイサービス(放デイ)に必要な職種について
放課後等デイサービスでは、児童福祉に関する専門職が多く働いています。職種についてそれぞれ見ていきましょう。
児童発達支援管理責任者
児童発達支援管理責任者とは、利用する児童・生徒に合わせた個別支援計画を作成したり、ご家族の子育てに関する相談支援を実施したり、療育支援が適切に提供されているかどうかモニタリングなどを行う職種です。
児童福祉分野または障害福祉分野における一定の経験を持ち、サービス管理責任者等基礎研修を修了した後、2年間のOJT期間を経て、サービス管理責任者等実践研修を修了することで正式に児童発達支援管理責任者として配置されることが可能となります。
児童発達支援管理責任者について詳しく知りたい方はこちらの記事をチェック!
 【2023年6月最新】児童発達支援管理責任者(児発管)とは? 資格の取り方・仕事内容・給料について分かりやすく解説
【2023年6月最新】児童発達支援管理責任者(児発管)とは? 資格の取り方・仕事内容・給料について分かりやすく解説
保育士
保育士とは、保育所などの児童福祉施設において子どもの保育を行う専門家です。放課後等デイサービスでは、個別支援計画に基づいた療育支援を提供します。
保育士になるには、厚生労働大臣が指定する学校や施設で必要な科目を履修した上で卒業し国家試験に合格するか、児童福祉施設で実務経験を積んだ後に国家試験に合格する必要があります。
放課後等デイサービスや児童発達支援で働く保育士の仕事内容について詳しく知りたい方はこちらの記事をチェック!
 児童発達支援・放課後等デイサービスでの保育士の働き方とは?
児童発達支援・放課後等デイサービスでの保育士の働き方とは?
児童指導員
児童指導員とは、児童福祉施設において子どもの療育や指導を行う職種です。放課後等デイサービスでは、保育士同様個別支援計画に基づいた療育を提供します。
「児童指導員」という資格は存在しないため、「児童指導員任用資格」を持つ者がその職に就くことができます。
児童指導員任用資格を持つ者とは以下に該当する者のことを指します。
- 社会福祉士または精神保健福祉士の資格保有者
- 幼稚園教諭、小・中・高の教員免許保有者
- 大学や大学院で社会福祉学、心理学、教育学、社会学を卒業した者
- 高校を卒業した者で、2年以上児童福祉事業に従事した経験がある者
- 3年以上児童福祉事業に従事した経験があり都道府県知事が適当と認めた者
児童指導員について詳しく知りたい方はこちらの記事をチェック!
 児童指導員とは?任用資格の要件や仕事内容、働く場所、給料について詳しく解説!
児童指導員とは?任用資格の要件や仕事内容、働く場所、給料について詳しく解説!
機能訓練担当職員(機能訓練もしくは重症心身障害児に支援を提供する場合)
機能訓練担当職員とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員のことです。
放課後等デイサービスでは、機能訓練を提供している事業所もしくは医療的ケアが必要な重症心身障害児に支援を提供している事業所に配置が必要で、心身のリハビリや日常生活動作の維持や向上といったケアを提供します。
機能訓練担当職員について詳しく知りたい方はこちらの記事をチェック!
 機能訓練指導員の仕事内容とは? 資格の取り方、取得メリットを解説
機能訓練指導員の仕事内容とは? 資格の取り方、取得メリットを解説
嘱託医(重症心身障害児に支援を提供する場合)
嘱託医とは、放課後等デイサービスに常駐していないものの、事業所からの委託を受けており、必要に応じて子どもの診察や治療を行う医師のことです。
放課後等デイサービスでは、医療的ケアが必要な重症心身障害児に支援を提供する場合に配置が必要です。
看護師(重症心身障害児に支援を提供する場合)
看護師とは、医療機関や福祉施設などで患者の療養上の世話を行う専門職です。
放課後等デイサービスでは、医療的ケアが必要な重症心身障害児に支援を提供する場合に配置が必要とされています。子どもたちの健康状態を管理したり、必要に応じて痰を吸引するなどの医療的ケアを行います。
放課後等デイサービス(放デイ)で役立つ資格
放課後等デイサービスで働く場合、発達障害などを持つ子どもを支援することから、障害者(児)支援や教育に関する知識や資格を持っていると就職や転職で有利となるケースがあります。
放課後等デイサービスで働きたい方は、就職や転職で役立つ資格の一部を紹介しますので、参考にしてみてくださいね。
社会福祉士
社会福祉士とは、日常生活における悩みや困りごとを抱えている方に対して、福祉に関する助言や支援を行う専門職で、ソーシャルワーカーと呼ばれることもあります。
大学等で指定された科目を履修して卒業し、国家試験に合格することで資格を得ることができます。
放課後等デイサービスでは、経験がなくても資格を持っていれば児童指導員として働くことができます。また、児童福祉や障害福祉の分野における一定の経験がある方は、児童発達支援管理責任者として働くための研修受講要件を満たしている可能性があります。
社会福祉士について詳しく知りたい方はこちらの記事をチェック!
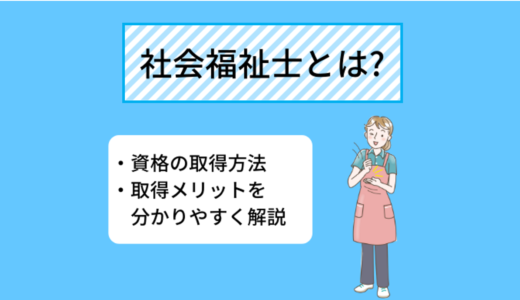 社会福祉士とは? 仕事内容や活躍の場、資格取得の方法や試験の合格率などについて分かりやすく解説
社会福祉士とは? 仕事内容や活躍の場、資格取得の方法や試験の合格率などについて分かりやすく解説
精神保健福祉士
精神保健福祉士とは、精神科領域を担当するソーシャルワーカーで、心に病を患う方や障害を抱える方に対して必要な支援を提供します。
大学等で指定された科目を履修して卒業し、国家試験に合格することで資格を得ることができます。
放課後等デイサービスでは、経験がなくても資格を持っていれば児童指導員として働くことができます。また、児童福祉や障害福祉の分野における一定の経験がある方は、児童発達支援管理責任者として働くための研修受講要件を満たしている可能性があります。
精神保健福祉士について詳しく知りたい方はこちらの記事をチェック!
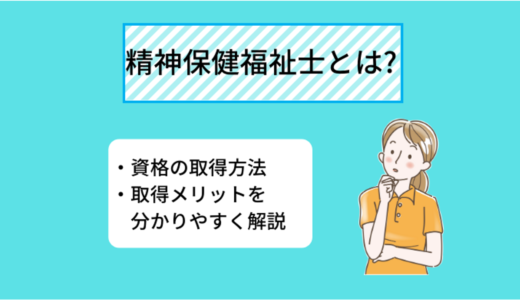 精神保健福祉士とは? 仕事内容、資格取得のメリットについて分かりやすく解説
精神保健福祉士とは? 仕事内容、資格取得のメリットについて分かりやすく解説
教員免許
教員免許とは、小学校、中学校、高等学校等の教育機関で教員として働くために必要な資格のことです。
大学等で指定された科目を履修して卒業し、国家試験に合格することで資格を得ることができます。
放課後等デイサービスでは、教員経験がなくても児童指導員として働くことができます。また、学校において障害児童などに対する相談支援や直接支援を行った経験が一定以上ある方は、児童発達支援管理責任者として働くための研修受講要件を満たしている可能性があります。
幼稚園教諭
幼稚園教諭とは、幼稚園において3歳から小学校就学前の子どもを教育する職種です。
一般的に大学等の教育機関で指定科目を履修した上で卒業することで、その資格を得ることが出来ます。
放課後等デイサービスでは、幼稚園教諭としての経験がなくても児童指導員として働くことが出来ます。幼稚園とは対象年齢が異なりますが、放課後等デイサービスは職員が一度に見る子どもの数が幼稚園と比較して少ないため、ブランクのある方にもオススメしたい職場と言えます。
理学療法士
理学療法士とは、病気やケガ・障害などにより、座る・立つ・歩くなどの基本的な動作についてリハビリを行う専門職です。
大学等で指定された科目を履修して卒業し、国家試験に合格することで資格を得ることができます。
放課後等デイサービスでは、機能訓練担当職員として、児童・生徒の日常生活動作の習得・向上により将来的に自立した生活を送ることができるようにするためのリハビリを提供します。
理学療法士について詳しく知りたい方はこちらの記事をチェック!
 理学療法士とは? 仕事内容、資格取得のメリットについて分かりやすく解説
理学療法士とは? 仕事内容、資格取得のメリットについて分かりやすく解説
作業療法士
作業療法士とは、病気やケガ・障害などにより、着替える・食事をする・遊ぶなどの日常生活における活動(作業)を通じたリハビリを行う専門職です。
大学等で指定された科目を履修して卒業し、国家試験に合格することで資格を得ることができます。
放課後等デイサービスでは、機能訓練担当職員として、児童・生徒が日常的に行う基本的な動作の習得・向上により将来的に自立した生活を送ることができるようにするためのリハビリを提供します。
作業療法士について詳しく知りたい方はこちらの記事をチェック!
 作業療法士とは? 仕事内容、資格取得のメリットについて分かりやすく解説
作業療法士とは? 仕事内容、資格取得のメリットについて分かりやすく解説
言語聴覚士
言語聴覚士とは、病気やケガ・障害などにより、話すことや聞くこと、食べることや飲み込むことのリハビリを行う専門職です。
大学等で指定された科目を履修して卒業し、国家試験に合格することで資格を得ることができます。
放課後等デイサービスでは、機能訓練担当職員として、機能訓練担当職員として子どもの発声に関する支援や、飲食におけるサポートを通して自立に向けたリハビリを提供します。
言語聴覚士について詳しく知りたい方はこちらの記事をチェック!
 言語聴覚士の仕事内容とは? 資格の取り方、取得メリットを分かりやすく解説
言語聴覚士の仕事内容とは? 資格の取り方、取得メリットを分かりやすく解説
公認心理師
公認心理師とは、心に悩みや問題を抱える人に寄り添い、問題解決に向けた適切な支援やアドバイスを行う専門職です。
大学等で指定された科目を履修して卒業し、国家試験に合格することで資格を得ることができます。
放課後等デイサービスでは、機能訓練担当職員(心理指導担当職員)として、児童・生徒のメンタルケアなどを行います。
公認心理師について詳しく知りたい方はこちらの記事をチェック!
 公認心理師とは? 仕事内容、資格取得のメリットについて分かりやすく解説
公認心理師とは? 仕事内容、資格取得のメリットについて分かりやすく解説
臨床心理士
臨床心理士とは、臨床心理学に特化した民間資格で、対象者の心の問題にアプローチする専門職です。
受験資格を満たした上で、日本臨床心理士資格認定協会が実施する試験に合格することでその資格を得ることが可能です。
放課後等デイサービスでは、機能訓練担当職員(心理指導担当職員)として、児童・生徒のメンタルケアなどを行います。
臨床心理士について詳しく知りたい方はこちらの記事をチェック!
 臨床心理士とは? 仕事内容、資格取得のメリットについて分かりやすく解説
臨床心理士とは? 仕事内容、資格取得のメリットについて分かりやすく解説
放課後等デイサービス(放デイ)で働くやりがい
放課後等デイサービスで働く方が、どのようなことにやりがいを感じながら働いているのかどうか、気になる方も多いのではないでしょうか。一例をご紹介します。
児童・生徒の成長や自立に携わることができる
障害の有無に関わらず、子どもが何かできるようになったり、自分の行動や感情をコントロールできるようになるなど、成長の瞬間に携わることができるのは喜ばしいことです。
一般的な教育機関等とは異なり、放課後等デイサービスは子ども一人ひとりとじっくり向き合えるため、児童・生徒の成長に密接に関わることができるということがやりがいの1つと言えるでしょう。
発達障害や教育・療育に関する知識を身につけることができる
放課後等デイサービスでは、様々な障害を持つ児童・生徒が利用しています。診断されている障害が同じであっても、一人ひとり強く出る障害特性が違っていたり、その程度が異なることは珍しくありません。また、効果的な対処方法も人によって違うことがあります。
そのため、放課後等デイサービスで働きながら障害について知識を深めたり、効果的な対処方法を身につけることができます。
子どもだけでなく保護者の支援もできる
放課後等デイサービスの支援内容の1つに「保護者支援」があります。
発達障害の特性などにより「周りの子はできるのにうちの子はできないこと」があったり、「周囲の状況に応じた対応が取れない」「問題行動がいつ出るか分からず困っている」などの悩みを抱えている保護者は多くいます。
そういった方のお話しを聞いたり、家庭での過ごし方のアドバイスを行うなど、子どもに対する支援だけが仕事でないことも魅力の1つと言えるでしょう。
経験を積んでキャリアアップを狙うことができる
放課後等デイサービスで保育士や児童指導員として5年間経験を積むことで、上位資格である児童発達支援管理責任者になるために必要な研修の受講要件を満たすことになります。
厚生労働省による「令和3年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果」を見ると、保育士や児童指導員の平均給与が311,050円であるのに対し、児童発達支援管理責任者の平均給与が388,340円で、77,290円も高いことが確認できます。
児童発達支援管理責任者となると給料が上がるだけでなく、知識や経験を活かして子どもたちの個別支援計画を作成できるようになるなど、担う業務の幅を広げることにもなります。
まとめ
今回は、放課後等デイサービスの仕事内容や必要な職種、持っていると役立つ資格、放課後等デイサービスで働くやりがいについて詳しく解説しました。
参考
e介護転職は、株式会社ベストパーソンが運営する、介護と福祉に特化した求人情報サイトです。
介護・福祉の求人情報を専門に扱う求人・転職サイトのため、介護・福祉の求人を探しやすいのが特徴です。
掲載求人件数は業界最大級で、全国の求人を取り扱っています。
介護・福祉に特化しているので、職種検索(介護職、ケアマネージャー、看護師、生活相談員、児童発達支援管理責任者、サービス管理責任者など)、サービス種類検索:介護(特養ホーム、有料老人ホーム、デイサービス、グループホーム、訪問介護など)・福祉の障害児/障害者支援関連(放課後等デイサービス、障害者就労支援など)、雇用形態での検索(正社員はもちろん、短時間パート、日勤のみ、夜勤のみなど)と充実しており、あなたに合った求人を探せます。
当サイトは、パソコンだけではなく、スマートフォンでも利用できます。これからの高齢化社会を支える業界で、是非あなたの力を発揮できる職場を見つけて下さい。
e介護転職に掲載している求人情報
- 介護職・ヘルパー
- サービス提供責任者
- 介護支援専門員
- 看護師
- 生活相談員
- 作業療法士
- 理学療法士
- 管理栄養士・栄養士
- 福祉用具専門相談員
- 福祉住環境コーディネーター
- 管理職
- 広報・営業職
- 介護事務・事務
- 送迎ドライバー
- 保健師
- 看護助手
- 言語聴覚士
- 医療事務
- 保育士
- 主任介護支援専門員
- 機能訓練指導員
- 相談員
- 訪問入浴オペレーター
- サービス管理責任者
- 児童発達支援管理責任者
- 児童指導員
- 調理職
- 支援員
- あん摩マッサージ指圧師
- 計画作成担当者
- 移動介護従事者(ガイドヘルパー)
- 居宅介護従事者
- 重度訪問介護従事者
- 行動援護従業者
- 相談支援専門員
- 臨床心理士
- 公認心理師
- 視能訓練士
- 技師装具士
- 手話通訳士
- 歩行訓練士
- その他








