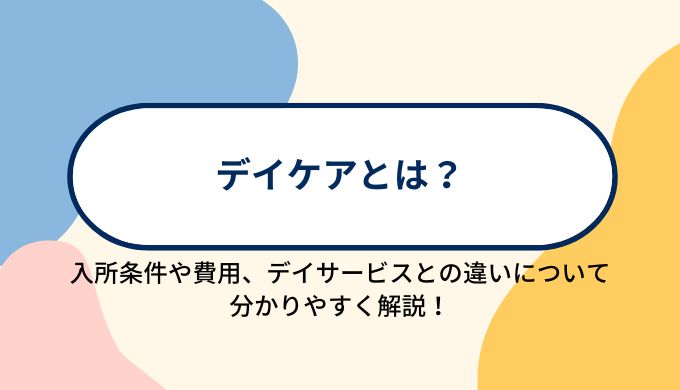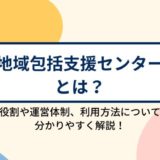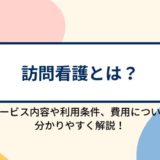要介護状態となるのを防ぐため、現状の身体機能を維持・向上させるために効果的なリハビリサービスを介護保険で受けられることができるのがデイケア(通所リハビリテーション)です。
今回は、デイケア(通所リハビリテーション)とデイサービス(通所介護)との違いや利用条件、利用にかかる費用などについて解説します。
デイケア(通所リハビリテーション)で働くことを検討されている方はこちらの記事をご覧ください。
 デイケア(通所リハビリテーション)とは?役割や人員基準、働くメリットなどを詳しく解説!
デイケア(通所リハビリテーション)とは?役割や人員基準、働くメリットなどを詳しく解説!
記事でわかること
デイケア(通所リハビリテーション)とは?
デイケア(通所リハビリテーション)とは、介護老人保健施設や病院、診療所(クリニック)などの施設において、自宅で生活を営む高齢者等に対し、日帰りで心身機能の維持回復を目的とした共通的サービスの他、利用者一人ひとりの状態に合わせて、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上を目的としたリハビリテーションを提供する事業所のことです。
要支援1~2及び要介護1~5の認定を受けていて自宅で生活を送る高齢者等が、日中事業所に通ってリハビリを受けることが可能です。
デイケア(通所リハビリテーション)とデイサービス(通所介護)の違いとは?
今回解説しているデイケア(通所リハビリテーション)とデイサービス(通所介護)は名前が似ていますが、その違いはどんなところにあるのでしょうか。一つずつ見ていきましょう。
対象者の要介護度
デイケアは要支援1~2及び要介護1~5の認定を受けた高齢者等ですが、デイサービスは要介護1~5の認定を受けた方のみで要支援1~2の方は利用することができません。
ケアの目的
デイケアの目的は、自立した生活に向けたリハビリを提供することですが、デイサービスは日中の生活支援を目的としています。
職員の体制
デイケアの職員体制の特徴として、医師が常駐していることと、国家資格を保有しているリハビリ専門職員が挙げられます。これに対し、デイサービスには医師がおらず、看護師が健康管理を行う他、機能訓練指導員がレクリエーションなどを通した機能訓練を行います。
デイケア(通所リハビリテーション)の設備とは?
デイケアにおいてリハビリテーションを行うための部屋は、利用定員に3㎡を乗じた面積が必要です。
また、リハビリに必要となる機器や器具についても備えておく必要があります。基準として必ずなければならない機器や数はないため、事業所ごとにどのようなものを揃えているか確認しておくと良いかもしれません。
デイケア(通所リハビリテーション)ではどんな人が働いている?
デイケアを利用する場合、どのような人が利用者の支援を行うのでしょうか。職種ごとに詳しく見ていきましょう。
医師
デイケアは専任の常勤医師を1人以上配置しなければならないとされています。ただし、病院、診療所と併設されている事業所、介護老人保健施設、介護医療院では、施設との兼務で差し支えないとされていますので、常に医師が利用者の様子を見てくれる状況であるということではありません。
利用者の心身の状態の把握と、一人ひとりに合わせたリハビリの計画を作成し、その指示を行うことが主な業務となります。
従事者
デイケアの従事者として、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、介護職員等が働いています。
従事者は、食事・排泄・入浴などの身体介助や日常生活援助を行います。この他、リハビリを兼ねたレクリエーションを行うこともあります。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
デイケアで提供されるリハビリテーションは、基本的に理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士といった国家資格保有者が行います。
医師の指示に基づいた一人ひとりの心身の状態に合わせて、自宅で自立した生活を送ることができるように、適切な機能訓練を実施します。
デイケア(通所リハビリテーション)を利用するメリットとデメリット
デイケアを利用するメリットとデメリットはどのようなところにあるのでしょうか。それぞれ詳しく見ていきましょう。
デイケア(通所リハビリテーション)を利用するメリット
デイケアを利用するメリットとして以下が挙げられるでしょう。
- 国家資格保有者による専門的なリハビリを受けることができる
- 医師が常駐しているので、医療的ケアを受けることもできる
- 訪問リハビリテーションと比較して、利用できるリハビリ機器や器具が充実している
デイケアでは、医師だけでなく理学療法士や作業療法士、言語聴覚士といったリハビリに特化した国家資格を保有した専門職員が働いています。そのため、必要に応じて医療的ケアを受けることができるだけでなく、自立に向けたリハビリを受けることができます。
また、自宅でリハビリテーションを受ける訪問リハビリテーションでは持参することができるリハビリ機器や器具に限界がありますが、デイケアでは様々な機器や器具を設置していることが多く、多角的なリハビリを受けることができるのもメリットの一つです。
デイケア(通所リハビリテーション)を利用するデメリット
デイケアのデメリットとして以下のようなことが考えられます。
- デイケア事業所の数がデイサービス事業所と比較して少ない
- 訪問リハビリテーションとは異なり、マンツーマンのリハビリではないこともある
デイケア事業所は、デイサービスの事業所と比較して少ないという実情があります。そのため、すぐに利用を開始したいと考えても定員がいっぱいで利用待ちとなる可能性があります。
また、自宅でリハビリテーションを受ける訪問リハビリテーションは、基本的に1対1でリハビリを受けることができますが、デイケアでは必ずしもマンツーマンでリハビリを受けられるというわけではありません。
デイケア(通所リハビリテーション)を利用する場合にかかる費用とは?
デイケアの利用を検討する中で、費用面の心配をされる方も少なくはないのではないでしょうか。
送迎を含めてサービスに係る費用は介護保険が適用となりますが、食費やおむつなどの日常生活費用は介護保健の適用となりません。
厚生労働省の「介護事業所・生活関連情報検索 介護サービス情報公表システム」によると、デイケアの自己負担額(1割負担)は以下の通りとされています。
要支援1~2の認定を受けた方の場合
| サービス費用の設定 | 自己負担額(1割の場合)/月 | |
| 共通的サービス | 要支援1 | 1,712円 |
| 要支援2 | 3,615円 | |
| 選択的サービス | 運動器機能向上 | 225円 |
| 栄養改善 | 150円 | |
| 口腔機能向上 | 150円 | |
参考:厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索 介護サービス情報公表システム「通所リハビリテーション(デイケア)」
要介護1~5の認定を受けた方の場合
※通常規模の事業所の場合(6時間以上7時間未満)
| サービス費用の設定 | 自己負担額(1割の場合)/回 |
| 要介護1 | 667円 |
| 要介護2 | 797円 |
| 要介護3 | 924円 |
| 要介護4 | 1,076円 |
| 要介護5 | 1,225円 |
参考:厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索 介護サービス情報公表システム「通所リハビリテーション(デイケア)」
デイケア(通所リハビリテーション)を利用する場合の流れとは?
デイケアを利用する場合の流れについて、ステップごとに詳しく見ていきましょう。
まとめ
いかがでしたか?今回は、デイケア(通所リハビリテーション)とデイサービス(通所介護)との違いや利用条件、利用にかかる費用などについて解説しました。
メリットとデメリットを考慮して、利用を検討される場合はデイケアを探してみてはいかがでしょうか。
デイケアでのお仕事に興味を持った方は、e介護転職であなたの希望に合う求人を探してみてくださいね。
参考
- 厚生労働省「通所リハビリテーション」
- 厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索 介護サービス情報公表システム「通所リハビリテーション(デイケア)」
e介護転職は、株式会社ベストパーソンが運営する、介護と福祉に特化した求人情報サイトです。
介護・福祉の求人情報を専門に扱う求人・転職サイトのため、介護・福祉の求人を探しやすいのが特徴です。
掲載求人件数は業界最大級で、全国の求人を取り扱っています。
介護・福祉に特化しているので、職種検索(介護職、ケアマネージャー、看護師、生活相談員、児童発達支援管理責任者、サービス管理責任者など)、サービス種類検索:介護(特養ホーム、有料老人ホーム、デイサービス、グループホーム、訪問介護など)・福祉の障害児/障害者支援関連(放課後等デイサービス、障害者就労支援など)、雇用形態での検索(正社員はもちろん、短時間パート、日勤のみ、夜勤のみなど)と充実しており、あなたに合った求人を探せます。
当サイトは、パソコンだけではなく、スマートフォンでも利用できます。これからの高齢化社会を支える業界で、是非あなたの力を発揮できる職場を見つけて下さい。
e介護転職に掲載している求人情報
- 介護職・ヘルパー
- サービス提供責任者
- 介護支援専門員
- 看護師
- 生活相談員
- 作業療法士
- 理学療法士
- 管理栄養士・栄養士
- 福祉用具専門相談員
- 福祉住環境コーディネーター
- 管理職
- 広報・営業職
- 介護事務・事務
- 送迎ドライバー
- 保健師
- 看護助手
- 言語聴覚士
- 医療事務
- 保育士
- 主任介護支援専門員
- 機能訓練指導員
- 相談員
- 訪問入浴オペレーター
- サービス管理責任者
- 児童発達支援管理責任者
- 児童指導員
- 調理職
- 支援員
- あん摩マッサージ指圧師
- 計画作成担当者
- 移動介護従事者(ガイドヘルパー)
- 居宅介護従事者
- 重度訪問介護従事者
- 行動援護従業者
- 相談支援専門員
- 臨床心理士
- 公認心理師
- 視能訓練士
- 技師装具士
- 手話通訳士
- 歩行訓練士
- その他