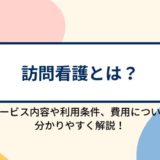2018年4月に創設された介護医療院という施設について、どんなサービスを受けることができるのか、どのような人が入所できるのかと気になる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、介護医療院のサービス内容と入所条件、入所にかかる費用などを分かりやすく解説します。
介護医療院で働くことを検討されている方はこちらの記事をご覧ください。
 介護医療院とは?施設の特徴や他の施設との違い、人員基準について詳しく解説!
介護医療院とは?施設の特徴や他の施設との違い、人員基準について詳しく解説!
記事でわかること
介護医療院とは?
介護医療院とは、長期的な医療と介護を必要とする高齢者に対し、日常的な医学管理や看取り、ターミナルケア等の医療的ケアと日常生活支援を一体的に提供する施設です。
2018年4月に創設された比較的新しい介護保健施設ですが、創設の目的として、高齢者が増加すると共に医療的ケアも必要な要介護者も増加するとして、こうした方のニーズを満たすために、具体的に以下のような体制を整えた施設が必要であるとされました。
- 経管栄養や喀痰吸引等の日常生活上に必要な医療処置や、充実した看取りを実施する体制
- 利用者の生活様式に配慮し、長期療養生活を送るのにふさわしい、プライバシーの尊重、家族や地域住民との交流が可能となる環境が整えられた施設
介護医療院には、Ⅰ型とⅡ型の2種類が存在します。それぞれの特徴を見ていきましょう。
介護医療院Ⅰ型
介護医療院Ⅰ型は、介護療養病床相当の施設として、重篤な身体疾患を有する方や身体合併症を持つ認知症高齢者などを主な対象者としています。
喀痰吸引や経管栄養を中心とした日常的且つ継続的な医学管理と、24時間の看取り・ターミナルケアを行う体制を整えており、入所者の容体が急変するリスクもあるなど、高い介護ニーズに対応しています。
介護医療院Ⅱ型
介護医療院Ⅱ型とは、老人保健施設相当の施設として、容体がⅠ型入所者よりも比較的安定した高齢者などを主な対象者としています。
日常的な医学管理と、オンコールによる看取り・ターミナルケアを行う体制を整えており、入所者の多様な介護ニーズに対応しています。
介護医療院の入所条件とは?
介護医療院に入所することができるのは、要介護1~5と認定された高齢者です。
特に要介護4や5などの介護度が高く医療の提供も必要とした高齢者が多く入所しています。
介護医療院の設備とは?
介護医療院には設備基準が設けられています。詳しく見ていきましょう。
| 設備等 | 基準 |
| 療養室 |
|
| 診察室 | 診察室は次に掲げる施設を有すること
|
| 処置室 | 処置室は次に掲げる施設を有すること
|
| 機能訓練室 | 内法による測定で40㎡以上の面積を有し、必要な機械及び器具を備えること。ただし、併設型小規模介護医療院にあっては、機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な機械及び器具を備えること |
| 談話室 | 入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること |
| 食堂 | 内法による測定で、入所者1人あたり1㎡以上の面積を有すること |
| 浴室 |
|
| レクリエーションルーム | レクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な設備を備えること |
| 洗面所 | 身体の不自由な者が利用するのに適したものとすること |
| 便所 | 身体の不自由な者が利用するのに適したものとすること |
参考:厚生労働省「介護医療院 公式サイト」
介護医療院ではどんな人が働いている?
介護医療院ではどのような職種の人が働いているのでしょうか。職種ごとにその業務内容も見ていきましょう。
医師
介護医療院には医師が常駐していることが特徴的です。病状の観察や看護師への医療行為の指示、薬の処方などのほか、急変時の対応も行います。
薬剤師
介護医療院では利用者に対して医師が薬の処方を行うことも多く、その薬を調剤するのが薬剤師の役目です。医師と看護職員、介護職員と連携して、利用者の内服薬等を管理します。
看護職員
看護職員は、医師の指示に基づいた医療行為や療養のお世話を行います。喀痰吸引や経鼻経管栄養、胃瘻や腸瘻の管理などの医療ケアの他、日々のバイタルチェックや健康管理を行います。
介護職員
介護職員は、食事・排泄・入浴等の身体介護及び、身の回りのお世話を提供します。医療ケアを提供する利用者が多いことからも、看護職員と密に連携して利用者のケアを行います。
リハビリ専門職
介護医療院で提供されるリハビリテーションを提供するのは、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士といったリハビリに関する国家資格を保有する専門職です。入所者一人ひとりに合ったリハビリを提供します。
栄養士(管理栄養士含む)
入所者の食事の献立作成や調理に携わる管理栄養士を含む栄養士が働いています。嚥下に困難がある方や、減塩食を摂る必要がある方など、様々な入所者の食事に対応しています。
介護支援専門員
介護医療院には、介護支援専門員が働いています。施設内でのケアプランを立て、適切な介護が提供されているかなど、入所者の様子をモニタリングします。
放射線技師
介護医療院では医療の提供もなされることから、放射線技師が配置されています。
介護医療院に入所する場合の費用とは?
介護医療院を利用する場合は、施設サービス費のほか、居住費・食費・日常生活費(理美容代金など)がかかります。
施設サービス費については介護保険が適用されるため、厚生労働省の参考元介護事業所・生活関連情報検索 介護サービス情報公表システムによると、自己負担額(1割)の場合は以下の通りとされています。
介護医療院Ⅰ型の自己負担額

参考:厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索 介護サービス情報公表システム「介護医療院」
介護医療院Ⅱ型の自己負担額

参考:厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索 介護サービス情報公表システム「介護医療院」
介護医療院に入所する場合の流れとは?
介護医療院に入所する場合、どのような流れとなるのか気になる方も多いのではないでしょうか。ステップごとに見ていきましょう。
まとめ
今回は、介護医療院のサービス内容と入所条件、入所にかかる費用などを解説しました。
高齢化が進む日本では、医療と介護の両者を受けられる施設として今後ますます需要が高まっていくでしょう。利用を検討されている方は、担当のケアマネジャー(介護支援専門員)や病院の医療ソーシャルワーカー等に相談してみてくださいね。
介護医療院のお仕事に興味を持った方は、e介護転職であなたに合う求人を探してみてはいかがでしょうか。
参考
- 厚生労働省「介護医療院 公式サイト」
- 厚生労働省「介護医療院の概要」
- 厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索 介護サービス情報公表システム「介護医療院」
- 独立行政法人福祉医療機構 WAMNET「介護医療院」
e介護転職は、株式会社ベストパーソンが運営する、介護と福祉に特化した求人情報サイトです。
介護・福祉の求人情報を専門に扱う求人・転職サイトのため、介護・福祉の求人を探しやすいのが特徴です。
掲載求人件数は業界最大級で、全国の求人を取り扱っています。
介護・福祉に特化しているので、職種検索(介護職、ケアマネージャー、看護師、生活相談員、児童発達支援管理責任者、サービス管理責任者など)、サービス種類検索:介護(特養ホーム、有料老人ホーム、デイサービス、グループホーム、訪問介護など)・福祉の障害児/障害者支援関連(放課後等デイサービス、障害者就労支援など)、雇用形態での検索(正社員はもちろん、短時間パート、日勤のみ、夜勤のみなど)と充実しており、あなたに合った求人を探せます。
当サイトは、パソコンだけではなく、スマートフォンでも利用できます。これからの高齢化社会を支える業界で、是非あなたの力を発揮できる職場を見つけて下さい。
e介護転職に掲載している求人情報
- 介護職・ヘルパー
- サービス提供責任者
- 介護支援専門員
- 看護師
- 生活相談員
- 作業療法士
- 理学療法士
- 管理栄養士・栄養士
- 福祉用具専門相談員
- 福祉住環境コーディネーター
- 管理職
- 広報・営業職
- 介護事務・事務
- 送迎ドライバー
- 保健師
- 看護助手
- 言語聴覚士
- 医療事務
- 保育士
- 主任介護支援専門員
- 機能訓練指導員
- 相談員
- 訪問入浴オペレーター
- サービス管理責任者
- 児童発達支援管理責任者
- 児童指導員
- 調理職
- 支援員
- あん摩マッサージ指圧師
- 計画作成担当者
- 移動介護従事者(ガイドヘルパー)
- 居宅介護従事者
- 重度訪問介護従事者
- 行動援護従業者
- 相談支援専門員
- 臨床心理士
- 公認心理師
- 視能訓練士
- 技師装具士
- 手話通訳士
- 歩行訓練士
- その他